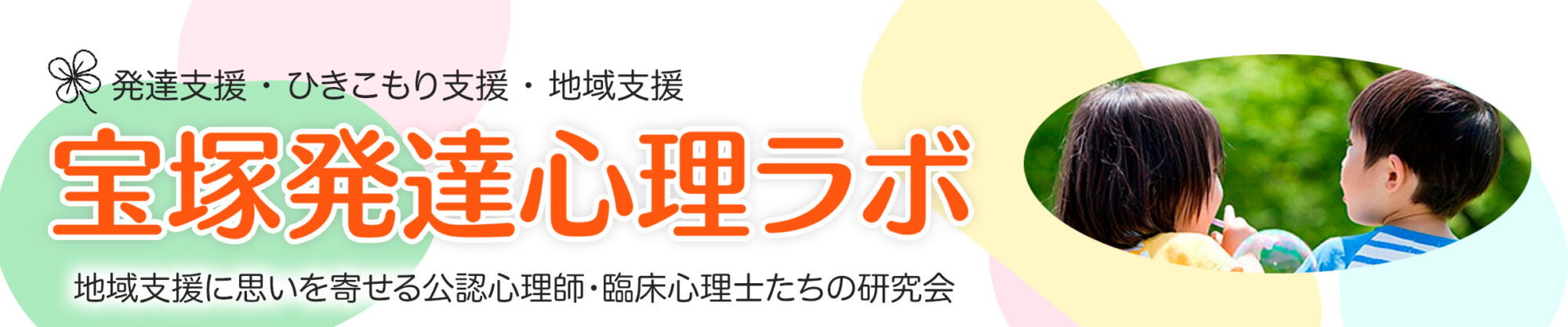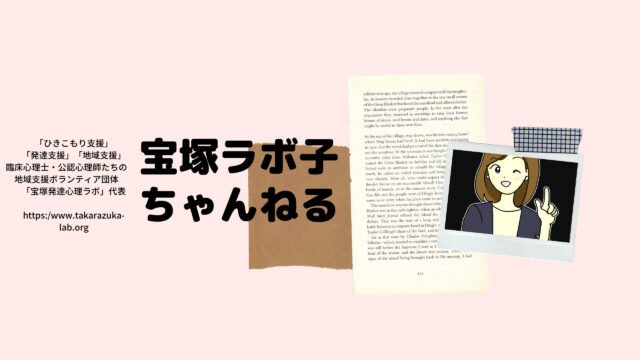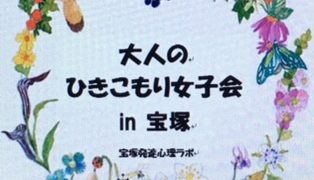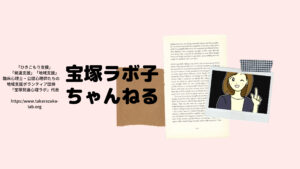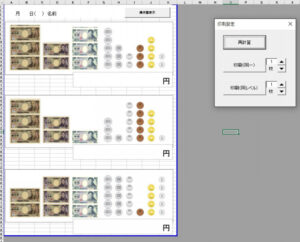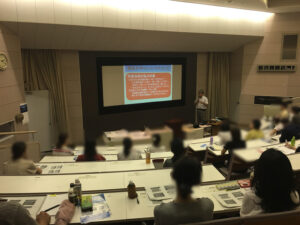不適応・トラウマを抱えた子どもへの支援のポイントは3つあります。

①安全・安心、安全基地、居場所があることです。そして、感情的に責めないこと。その子を支配しないようにすることが大切です。
②2番目は共感性です。こどもの言ったことについて「そうだよね。」と共感性を高めていくことが大切です。そして基本的自尊感情を高めていくことです。
褒められたら高まるほうの社会的自尊感情ではなくて、その子の存在そのものを大切に思うほうの基本的自尊感情です。
「いい子だから好き」「〇〇できる子だから好き」なのではなくて「その子の存在自体にすでに価値がある」といった感情を一体どれくらい伝えられているでしょうか。
「生まれてきてくれてありがとう。」この気持ちが大切なのです。というか、これさえあれば実はもう他はいらないかもしれません。
③総合的で柔軟であることです。
規則に柔軟である、カリキュラムに柔軟であることが大切です。そう考えると不適応を起こした子どもには、日本の学校は規則でガッチガチ、授業も文科省からのカリキュラムの縛りがありますのでかなり過ごしにくい場所かもしれません。
フリースクールが市民権を得ている時代ですから学校にどうしてもなじめなければ環境を変えてしまうというのも方法としてありかなと思います。ただしこれはかなり勇気がいることなのです。
というのは今、発達障害のあるこどもを育てている親御さんたちは人と同じことをすることにものすごく価値を置かれる方が多く転校なんてありえないかもしれませんね。
でもその「人と同じことをさせたい」気持ちが子どもたちに伝わってしまうのです。そうすると、「学校にいけない。」「勉強ができない。」という現実に「おれはダメだ・・・。」とペシャンコになってしまうのです。
そうならないお子さんはきっと家の中でありのままの姿を認めてもらえているのだと思います。
学校に行っていても行かなくてもどちらも君であることには変わりない。そんな君が好きだよと。基本的自尊感情についてですがその子の存在そのものを大切に思う「生まれてきてくれてありがとう」の気持ちがどこまでも大切で、これが子どもたちに伝わってこそどんな支援も生きてくるのです。